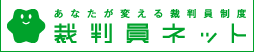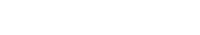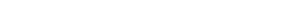![]()
最高裁判所が2008年4月1日に発表した「裁判員制度に関する意識調査」では、裁判参加時の心配及び支障について「判決で被告人の運命が決まる責任を重く感じる」と回答した人が全体の75.5%でした。しかし、人を裁きたくないことを理由に裁判員になることを拒むことができるかどうかについては、裁判員法に明確に規定されていません。
人を裁きたくないことを理由として裁判員になることを拒む「良心的裁判員拒否」が認められるかどうかは、裁判員候補者にとっては切実な問題です。
そして、「良心的裁判員拒否」という選択肢をつくることができるかどうかは、今後の裁判員制度の運用次第であると言えます。
![]()
「一人で責任を負うのではなく、皆で意見を言って結論を出す。そんなに重く感じる必要はない。」(『朝日新聞』2008年5月3日)
「有罪であれば極刑(死刑)が相当な重罪で、被告人が犯人であるか否かが激しく争われている場合の事実認定は重大である。死刑か無罪か、被告人にとっては地獄か天国かの違いであり、被害者(あるいはその遺族)にとっても、捜査従事者や被告人の支援者など事件関係者にとっても、深刻な問題である。裁判の結果が社会に与える影響も少なからぬものがある。」「いかにして正しい事実を認定するか。これが刑事裁判の中心的な課題であり、刑事裁判に関係する者の絶えざる関心事である。そして、適正な事実認定が実は容易ならざるものであることも、関係者が等しく痛感しているところである。」(石井一正『刑事事実認定入門』)
量刑は、「裁判官が、その職業的良心と全人格をかけて、被告人の罪と罰を直視し、その人間を見極めた上でなされる作業」である。(岩野壽雄『罪と罰-量刑に悩む元裁判官の手記』)
(最高裁判所「裁判員制度に関する意識調査」2008年4月)
![]()
良心的裁判員拒否とは、人を裁く重みを感じた人が、自分は人を裁くことはできないと思った場合、裁判員になることを拒むことです。
人を裁くことの重みを感じることが一枚のコインだとすれば、そのコインの表が責任ある参加であり、裏が良心的裁判員拒否となります。この二つは表裏一体で、どちらも人を裁く重みを感じ一人ひとりが主体的に行動するものです。
もし裁判員を拒否した人が代替的に刑事司法の分野でボランティアや寄付をできるようにすれば、裁判員となった人だけが負担を負うことにはなりません。むしろ代替的な方法があれば、裁判だけではなく、刑事司法について幅広い関心を喚起することになります。
良心的裁判員拒否は、辞退事由の解釈や選任手続の運用によって実現する可能性があります。立法過程で「思想・信条の自由」という憲法上の問題から政令で辞退理由を追加するとの閣議決定がなされた経緯もあります。
良心的裁判員拒否を認めると、面倒くさいと思うだけの人と区別がつかないとの意見もあります。しかし、もし制度が維持できないほどの多数の国民が安易な言い訳として良心的裁判員拒否を持ち出すのであれば、残念ながら司法を国民が直接担う時期でないということになります。真摯にその状況を受けとめ、裁判員制度の一時停止か廃止をすべきでしょう。