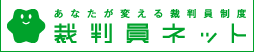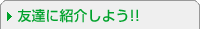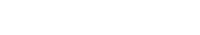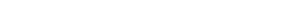第13回裁判員制度フォーラム「市民参加の意義と課題を考える」を開催しました
2015年11月27日
2015年11月21日(土)は裁判員制度が開始されてから、6年半になります。それに先立つ11月15日(日)、専修大学 にて裁判員ネット第13回裁判員制度フォーラム「市民参加の意義と課題を考える」を開催しました。当日は大勢の皆さまにご来場いただきました。本当にありがとうございました。
全国初の裁判員裁判と同時にスタートした「裁判員裁判市民モニター」には、この6年半の間に約320名の方が参加しました。モニタリング件数は620件を超えます。また、裁判員裁判を傍聴した後に行っている「模擬評議」は33件実施し、これまでに延べ277名の方が参加しました。
こうして13回目となるフォーラムを開催できたのも、皆さまのご支援、ご協力があってのことです。あらためてお礼を申し上げます。
■第1部レポートセッションより
このフォーラムの第1部・レポートセッションでは、裁判員制度市民モニターとして裁判員裁判の傍聴・模擬評議を行った事例を詳しく取り上げ、モニター参加者からの意見を紹介しながら、市民の視点から見えた裁判員制度の現場や課題について、メンバー自身の経験を踏まえながら報告を行いました。
2015年6月5日、裁判員法が改正され、今回の改正法の施行から3年後に再び制度の見直しを検討することが盛り込まれました。裁判員ネットは、今後のさらなる制度の見直しに向けて、市民の視点から裁判員制度のあり方を検証することがさらに大切になってくると考えています。
レポートセッションでは実際に裁判員制度が行われる中で見えてきた課題についても、いくつかの論点をピックアップしてご紹介しました。
■第2部トークセッションより
続く第2部ではゲストをお迎えして、「市民参加の意義と課題」についてトークセッションを行いました。パネリストとしてゲストの専修大学准教授・飯考行さん、裁判員ネット代表・大城聡、大学生で裁判員ネットインターン生の水沼春菜さんが登壇。コーディネーターは坂上が務めました。
・市民が司法に参加する意義と課題
「市民参加の意義と課題」について意見を交わすにあたって、まず飯先生よりお話をしていただきました。飯さんは「現在、裁判員候補者の選任手続きへの出席率が年々低下し辞退率も上昇する傾向にあることは、裁判員制度の意義がはっきりと語られていないことに原因がある。また裁判員制度の意義は、国民の司法に対する理解を増進し信頼を向上させることにあるというのが最高裁の見解だが、むしろ意義は『市民が司法に対してチェック機能を果たすこと』にあるのではないか」、といったお話をして下さいました。
こうしたお話を伺うなかで、なぜ私たち市民が司法に参加するのか、原点に立ち返って裁判員制度の意義を見つめ直すことが、制度を市民の視点から検証するうえで必要なのだと感じました。
・裁判員裁判を自分たちの問題として考える
市民が司法に参加する意義についての議論を一歩深めるために、客席の皆さんにも参加をしていただきました。ここでは皆さん全員に赤と青の2色のカードを配布し、二者択一の問いかけに対し「YESであれば青」「NOであれば赤」など色カードを提示してお答えいただく形式をとり、様々な問いかけを行いました。
みなさんに「裁判員になりたいか」ということについてお聞きしたところ、会場からは「裁判員になりたい」という青のカードと「なりたくない」という赤のカードが半々に上がりました。この点について裁判員候補者の選任手続きの出席率の低下と辞退率の上昇が見られる現状と併せて、パネリストで議論を行いました。議論では、「裁判員になりたくない」と思う裁判員候補者が多く見られる理由の一つとして、裁判員制度自体が市民の間に根付いておらず、「自分たちの問題として意識することがないからではないか」ということが指摘されました。
また、大学生の水沼さんからは、「20歳になった時『選挙権を得た』とは思ったが、同時に『裁判員になるかもしれない』という意識には結びつかなかった」と話しました。
質疑応答では、なぜ裁判員制度が市民に浸透していないのか等、多くの方に質問をしていただき、会場内では活発な議論が行われました。
裁判員制度は市民参加の制度です。市民は新たな「司法の担い手」となりました。私たち市民にとって、もはや刑事司法は「他人事」ではなく、「自分たちの問題」として主体的に考えていくことが必要です。市民が、市民参加の意義を考え、問いを発し合って議論することによって、主体的な参加が実現するのだと考えます。
これからも裁判員ネットでは、裁判員制度フォーラムや講座・出張授業などを通じ、多くの皆さんとともに市民の視点から裁判員制度について考える機会をつくっていきたいと思います。
次回第14回フォーラムは2016年5月下旬頃を予定しております。
今後ともお力添えのほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
(裁判員ネット・坂上暢幸)