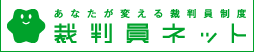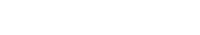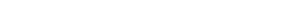【講演録】「裁判員になるかもしれないあなたへ」① 裁判員ネット代表・大城聡
2010年4月23日
裁判員ネット代表理事の大城聡が、情報懇話会第197回例会(2009年12月16日)にて「裁判員になるかもしれないあなたへ」というテーマでお話する機会をいただきました。
「情報懇話会21」会報No.191(連合通信社)にまとめられた例会の様子を本コラムで紹介したいと思います。(全5回)
この講演について、皆さまのご質問、ご意見もお待ちしております。ご質問、ご意見のある方はinfo@saibanin.netまでお気軽にご連絡ください。
**************************************************
「裁判員になるかもしれないあなたへ」①
□刑事裁判の最大の使命は「冤罪」を防ぐこと
□無実の人がなぜ「自分が犯人だ」と自白するのか
□足利事件にみる「自白」の強要
□“これまでの刑事裁判の評価”が棚上げされた結果、裁判員制度が実現
**************************************************
弁護士の大城です。「裁判員ネット」という市民グループを立ち上げて市民の視点から裁判員制度を考える活動をしています。裁判員ネットは一般社団法人として弁護士だけではなく、会社員や学生、臨床心理士も運営に携わっています。
□刑事裁判の最大の使命は「冤罪」を防ぐこと
日本に導入された裁判員裁判はいま、刑事事件だけで行われています。そこで、最初に刑事裁判の最大の使命は何かということを確認してから、裁判員制度を考えていきたいと思います。
刑事裁判の役割はいろいろあります。例えば、どんなに極悪人でも適正な裁判を受けて刑罰を受けられるようにする役割があります。また、有罪の場合には刑罰を決める量刑の判断という役割もあります。量刑の中でも懲役で刑務所に行く実刑なのか執行猶予なのか難しい判断をする場になることもあります。時には裁判の中で罪を犯した人を反省し更生させるという役割もあります。刑事裁判にはいろいろな役割があるのですが、その中でも最大の使命は、「冤罪」を防ぐことです。「冤罪」とは無実の人が間違えて犯人とされて刑罰を受けることです。ちょうど今朝の新聞各紙に報道されている「布川事件」もその代表例だと言えます。この事件は43年前の強盗未遂事件です。
布川事件では、捜査段階では「自分たちが犯人である」と自白していました。しかし、裁判では「犯人ではない」と否認し続けました。しかし、第一審で有罪、控訴審でも有罪、最高裁でも有罪の判決は覆りませんでした。40年以上の時を経て、ようやく再審への扉が開かれたのです。再審というのは裁判のやり直しです。この再審ではかなり高い可能性で無罪になるだろうと見られています。
冤罪について、最近では「足利事件」の菅家さんのことも広く報道されています。報道を通じて冤罪の恐ろしさに対する認識も広がっているのではないかと思います。
何よりも怖いのは、本当に何もしていない人が無実の罪で刑務所に入れられてしまうことです。一方で真犯人は野放しになってしまいます。刑務所に入れられたのが無実の人であれば、真犯人は捕まっていないことになります。足利事件のように時効になればもう真犯人を検挙することはできません。被害者にとっても犯人が野放しになっていることは耐えられないことです。このような冤罪を防がなければいけないというのは、弁護士、検察官、裁判官に共通の認識です。しかし、どのように冤罪を防ぐかということには、それぞれの立場から見解の違いがあるように思われます。
□無実の人がなぜ「自分が犯人だ」と自白するのか
冤罪事件に共通するのは過酷な取り調べと「自白」偏重の問題です。裁判官は「犯人であることを認めたら死刑になるかも知れない場合、自分が犯人だと認めるわけないだろう」と考えて、結局、一度自白したことを信用して有罪にしてしまうのです。足利事件の菅家さんの場合、DNA鑑定など、科学捜査を間違えたと言われています。しかし、実は足利事件では無実のはずの菅家さんが捜査段階と第一審の途中までは「自分がやりました」と自白していたのです。
なぜ本当は犯人ではないにもかかわらず自分が犯人だと言ってしまうのか。その鍵は密室での過酷な取り調べにあります。
□足利事件にみる「自白」の強要
先日、菅家さんから直接お話を聞く機会がありました。菅家さんが逮捕された時、自宅のドアを叩く音がするのでドア開けると警察官がいきなり入ってきたそうです。それから警官に肘鉄砲でみぞおちの所を突かれて、そのまま菅家さんは窓ガラスに吹っ飛んでぶつかり畳に落ちました。そうすると警官は、菅家さんに対して、殺された少女の写真を目の前に突きつけて「お前、この子に謝れ」と、大きな声で怒鳴りました。地元で大きく報道されたので事件のことを知っていた菅家さんは可哀相だなと思って手を合わせました。それを見た警官は「やっぱりお前がやったんだ」と言って、菅家さんを連れて行きました。
驚くべきことに菅家さんを支援してきた弁護士の話では、その時に逮捕令状がなかったということです。逃げようとしていないのにいきなり肘鉄を食らわせることや「お前がやったんだ」などと言うことは、令状を持った逮捕の時でも許されないことです。そのようなことを令状なしでしていたのです。
布川事件の記事を見ますと、朝から晩まで犯人扱いで何を言っても聞いてくれないと書いてあります。菅家さんも全く同じことを言っていました。さらに菅家さんは、「科学捜査で犯人はわかっている」と言われました。当時はDNA鑑定が始まったばかりでした。菅家さんは「何を言ってもだめだ。どうしたら取り調べをやめてくれるだろう」と思ったそうです。そこで心が折れて「私がやりました」と言ったのです。人間がこのような過酷な状況に置かれた時、これは決して珍しいことではないのです。布川事件でも足利事件でも、厳しい取り調べを受けて、その場で「自分が犯人だ」と言ってしまうのです。もう一つそこに共通している点は、裁判では「自分は犯人ではない」ということを裁判官はわかってもらえると思うことです。しかし、裁判官は、裁判の時になって「犯人ではない」と
言っても信用せずに、捜査段階で「自白」した書面のほうを信用したのです。
本来、刑事裁判では、たとえ10人のうち9人の真犯人を逃したとしても、1人の無実の人を罰してはいけないのです。刑事事件の最大の使命は無実の人を間違えて罰しないようにチェックすることなのです。取り調べの時だけではなく、裁判の時にも「自分が犯人だ」と言ってしまう人もいます。富山の強姦事件で捕まった人は裁判の時もあきらめて「自分が犯人だ」と言っていたのです。ところが、刑務所での懲役刑を終えた後に真犯人が出てきました。「自白」だけに頼る自白偏重が危険なものであることを物語っています。刑事裁判の最大の役割である「冤罪を作らない」ことは実はとても難しいことでもあるのです。
□“これまでの刑事裁判の評価”が棚上げされた結果、裁判員制度が実現
冤罪を防ぐことが最大の使命である刑事裁判に裁判員制度が導入されるということが、裁判員制度を考える時の一番大事なポイントです。アメリカの陪審員制度は刑事事件だけでなく民事事件の一部にも導入されています。しかし、日本の裁判員制度は刑事裁判だけが対象です。このことを念頭に置きながら、今日はぜひ皆さんと考えていきたいと思います。
裁判所、検察、弁護士の立場からこれまでの刑事裁判をどのように評価するかを考えてみます。裁判所はこれまでの刑事裁判は正しかったという立場です。判決をする立場ですから自己否定はできないのです。また、検察もこれまでの刑事裁判は正しかったという立場でしょう。日本の有罪率は99%以上です。つまり検察が起訴したらされたらほぼ確実に有罪になるのです。だから、検察もこれまでの刑事裁判は正しいという立場です。
一方で弁護士の中では、冤罪もあり、これまでの刑事裁判に問題があるという意見が多くあります。裁判所は、被告人が「私はやっていません」と言ったとしても、「いやいや、かつて自白して指印まで押している書面がある。書面を信じる」としてきたのです。このような自白偏重、書面重視の裁判が冤罪を生んできたのだと考える弁護士が多くいます。これまでの問題ある刑事裁判を変えるために陪審制度や裁判員制度のような市民参加が必要だという立場です。
このように、これまでの刑事裁判に問題があるから裁判員制度で変えるのだという考え方と、これまでの刑事裁判は良かったけれども市民参加も認めるという考え方があるのです。この二つの考え方では、裁判員制度がなぜ必要かという理由が大きく異なります。一般にある制度を導入する場合には、その制度が必要な理由をまず明確にします。
ところが、これまでの刑事裁判が良かったのか悪かったのかということを議論すると、検察、裁判所、弁護士会の立場は鋭く対立してまとまらないわけです。そこでどうしたかというと、これまでの刑事裁判の評価を「棚上げ」したのです。弁護士会ではアメリカのような陪審員制度を推す人が多かったようです。しかし、市民参加に大きな意味があるからと裁判員制度に賛成しました。
最高裁は当初は反対していました。参考に意見を聞くだけならいいが、評決に加わらせるのはまだ早いとコメントをしていたのです。しかし、途中から市民参加に賛成するようになりました。その大きな原因は、これまでの刑事事件の評価をしないという暗黙の合意があったからではないでしょうか。結局、裁判員制度の導入に際して、これまでの刑事裁判に対する評価というのは明確になされませんでした。つまり、過去の評価をしないで、制度の変革がなされたのです。いわば誕生の時から妥協の産物であったのです。まさに呉越同舟です。裁判員制度が「なぜ始まったか」と一言で説明できないのは、このような経緯で制度が生まれたからなのです。
裁判員制度が始動した今、私たちは裁判所、検察、弁護士会だけに「お任せ」するのではなく、今度は「なぜ裁判員制度が必要か」という根本的な議論を市民の間で幅広く行う必要があるのだと思います。
裁判員ネット代表理事・大城聡
(第2回に続く)