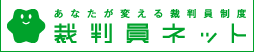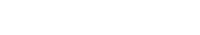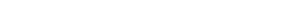裁判員裁判の現場から―市民モニターの声⑦
2012年2月4日
裁判員ネットでは、市民による裁判員裁判の傍聴と、傍聴した裁判について自分たちなりの「判決」を出してみるという「模擬評議」のふたつから成る「裁判員裁判市民モニター」を実施しています。2012年2月現在、170名を超す方に市民モニターとして裁判員裁判を傍聴していただいております。
ここでは、市民モニター終了後にお寄せいただいた裁判についてのご意見やご感想のうち、了承を得たものについて紹介いたします。
■初めての裁判傍聴を終えて
私にとっては今回が初めての裁判傍聴でした。学問や仕事、その他何事についても言えることだと思いますが、遠くからは全てが激動し、感動的な示唆と驚きに満ち溢れたものに見えるのに、一度その中に飛び込んでみると、いかに地道な作業の積み重ねの上にそれが成り立っているかが分かります。今回の裁判傍聴も、そのような経験の一つであるように思われます。
モニターシートの記入やディスカッションを通して、今回の経験についてじっくり考えているうちに、自分の認識している法学の枠組みの中に「訴訟法」という新たな地平線が開けてきたのではないか、という気がしてきました。刑法の試験問題には、犯人に故意があったかなかったか、錯誤があったかなかったかというようなことは全て書かれています。実際の裁判ではそういった点が争われるのだろうとは思っていましたし、刑事裁判の手続きが刑事訴訟法で定められている、という程度の認識はありました。しかし、実際の裁判を傍聴するまでは、この2つが私の中ではうまく噛み合っていなかったのです。図書館へ行くと、訴訟法の棚で裁判官の事実認定に関すると思われる本をいくつか発見することができました。ああこれを巡って争っていたのかと、非常に新鮮な驚きを感じました。裁判所に赴き、現場を見たことによって大きな意義のある発見ができました。
実際に裁判を傍聴することで、裁判員になることが一般市民に大きな肉体的・精神的負担を強いることはすぐに分かりました。私にとってむしろ重要だったのは、もし自分が裁判員になったとして、よく言われる「人を裁くことの精神的重圧」をきちんと感じることができるだろうか、ということです。
裁判員はほぼ無作為に「選ばれる」ものであり、自分の意思で「なる」ものではありません。中には普段の仕事に支障が出ることへの不満を持つ人もいるでしょうし、なんで私がこんな面倒を、と思う人も少なくないのではないかと思います。また、どんなに真剣に裁判に取り組んだとしても、それを評価してくれる人は法廷の外にはいないのです。このような条件の下で、私は果たしてどれほど真剣に赤の他人である被告人について考え、「精神的重圧」を感じることができるだろうか、と思うのです。
自分の判断で他人の人生を左右する重圧に苦しむのも人間ですが、『12人の怒れる男』に登場する面々の思い(どうせこいつが犯人に決まっている、面倒だからさっさと終わらせよう)もまた、それと同じくらいありふれた人間の姿だろうと思うのです。果たして自分がどのような心持ちで裁判員裁判に臨むことになるのか、その答えはまだ見つけられずにいます。
(宗伸一郎)
■「正解」がわからないまま判断を下す難しさ
今回私が傍聴したのは、被告人が有罪か無罪かを判断しなければならない裁判でした。今まで私は何度か裁判を傍聴してきましたが、このような、言わば100か0かを決めるケースの裁判を傍聴するのは初めてで、雰囲気の重さを感じずにはいられませんでした。
しかも、今回の裁判では被告人は完全黙秘を貫いており、全く「声」を発することがありませんでした。自分が事件当日どこにいて、何をしていたのか、さらには自分の名前さえも証言しませんでした。私は、被告人が何一つ「声」を出さないということ、そして被告人抜きで裁判がどんどん進んでいくということに恐ろしさのようなものを感じました。有罪か無罪かを争う裁判であるのに、被告人は何一つ「声」を出さないのです。それは、「どうせ、有罪になるのだから反論するだけ無駄だ」など、被告人なりの考えがあってのことなのかもしれません。しかし、それはあくまで私の想像でしかありません。本当のことを知っているのは被告人だけなのであり、それを確かめる術はないのです。
今回、被告人が完全黙秘に徹した裁判の傍聴を通じて、今までの裁判で私がいかに被告人の言葉に重きを置いていたのかを痛感させられました。本来ならば被告人を中心にして進んでいくところを被告人抜きで進んでいった今回の裁判では、決定的といえる証拠が何一つ上がらず、被告人が本当に犯人であると言えるのかという疑いにますます拍車を掛けているように感じました。そのような中で弁護側や検察側が必死に証拠と被告人との関連性の有無について語っても、私はいまひとつリアリティを感じることができませんでした。
こうした経験を通じて、私が一番考えさせられたことは、検察の立証責任についてです。刑事裁判の原則として、本来ならば、少しでも疑わしき事情があるのならば、被告人は無罪とすべきということが言えます。一方で、その疑いがあくまで抽象的なものであるならば、検察の立証責任を侵害するには至らないという但し書きがつけられています。今回のケースでは、弁護側は合理的な疑いが残ると主張し、検察側は弁護側の主張する疑いはあくまで抽象的なものだとして、真っ向から意見がぶつかり合っていました。私が論告・弁論を聞いたときはどちらの言い分にも一理あると感じられ、どちらが「正しい」のかは全くわかりませんでした。「合理的な疑い」と「抽象的な疑い」の間に明確な線引きがなされているわけではない以上、どちらの言い分にも納得できる部分があるので、簡単に決めることはできないと感じました。これを、裁判員に選ばれた一般市民は決めなければならないのです。司法に関して全くの素人である一般市民が判決を下さなければならないということは、相当酷なことだろうと私は感じました。今回のような100か0かを決める場合ではその責任もより一層大きなものになります。裁判員の精神的負担を考慮した場合、今回の事件は非常に難しいものだったのではないか、そのように私は今回の裁判を傍聴して感じました。
(爲田世良)